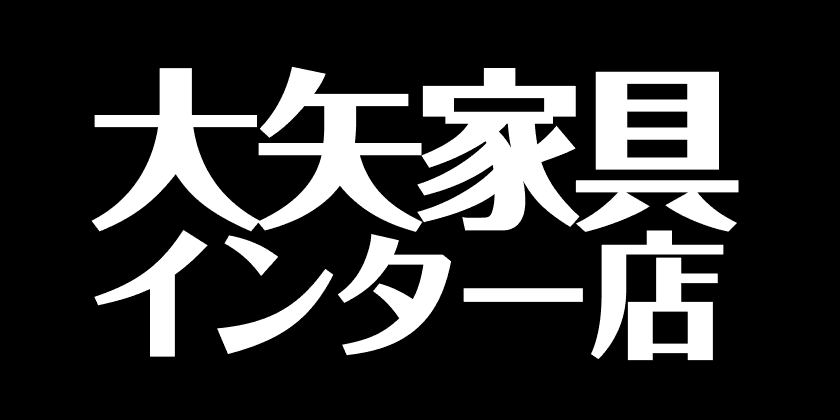「すのこベッドはやめたほうがいい」と耳にしたことはありませんか?通気性に優れ、湿気対策に効果的とされるすのこベッドですが、実際に使用した人の中には後悔している方もいるようです。
このコラムでは、名古屋市名東区にある大矢家具店のベテランスタッフが、すのこベッドのデメリットと対策について詳しく解説します。
すのこベッドとは?
すのこベッドとは、ベッドの床板部分がすのこ状になっているベッドのことです。木材や樹脂の板を一定の間隔をあけて組み合わせた構造で、一般的なベッドと比較して優れた通気性を持っています。すのこベッドは、湿度の高い日本の気候に適したベッドとして人気を集めており、カビやダニの発生を抑制する効果が期待できます。素材も桐・檜・杉・パイン材など多様で、それぞれ異なる特性を持っています。
一方で、その特殊な構造ゆえに、購入後に「やめたほうがよかった」と後悔する方もいるのが実情です。
すのこベッドで後悔する主な理由

すのこベッドで後悔する理由は数多くあります。ここでは、すのこベッドで後悔する具体的な理由について詳しく解説します。
冬場の冷えが厳しい
すのこベッドの最大の特徴である通気性の良さが、冬場はデメリットになることがあります。床からの冷気がすのこの隙間を通って直接身体に伝わるため、特に薄い布団を使用している場合は寒さを感じやすいです。マンションのコンクリート床やフローリングの上では、冷えがより顕著に現れることがあります。
きしみ音が気になる
すのこベッドは複数のパーツで構成されているため、寝返りの際に「ギシギシ」という音が発生することがあります。特に安価な製品では、組み立ての精度や素材の品質によって音が出やすい傾向があります。音に敏感な方や、家族と一緒に寝室を使用している方にとって、きしみ音は大きなストレスになるかもしれません。
寝心地の硬さ
すのこベッドは構造上、一般的なベッドの床板より硬めの寝心地になりがちです。薄いマットレスや敷布団を使用した場合、すのこの凹凸を感じて不快に思う方もいます。腰痛持ちの方や、柔らかい寝心地を好む方には向かない場合があることを理解しておきましょう。
すのこベッドのデメリットは解消できる
すのこベッドのデメリットは、適切な対策を講じることで大幅に軽減できます。ここでは、具体的な対策方法について紹介します。
冷え対策
冬場の冷えには以下の対策が効果的です。
- ベッド下にラグやカーペットを敷く
- 厚手の敷きパッドやマットレスを使用する
- 電気毛布や湯たんぽを活用する
通気性を完全に遮断しない範囲で対策を行うことが、すのこベッドの本来の機能を活かしながら快適性を保つポイントです。
きしみ音の対策
きしみ音の対策としては、以下のような方法があります。
- 定期的なネジの増し締め
- 接触部分へのクッションテープの貼付
- 高品質なすのこベッドの選択
購入時に耐荷重や構造をしっかり確認することで、音が出にくい製品を選ぶことができます。
寝心地の改善
硬さが気になる場合は、以下の対策を検討しましょう。
- 厚みのあるマットレスの使用
- マットレストッパーの追加
- 体圧分散性に優れた寝具の選択
適切な寝具を組み合わせることで、すのこベッドでも快適な睡眠環境を実現できます。
すのこベッドのメリット

すのこベッドにはデメリットだけではなく、メリットも存在します。ここでは、すのこベッドのメリットについて詳しく解説します。
優れた通気性とカビ対策
すのこベッドの通気性の良さは、湿気の多い日本の住環境において大きなメリットとなります。マットレスや布団の湿気を効率的に逃がし、カビやダニの発生を抑制する効果が期待できます。
メンテナンスのしやすさ
軽量なすのこベッドは移動が容易で、掃除やレイアウト変更の際に便利です。ベッド下の清掃も簡単に行えるため、清潔な睡眠環境を維持しやすいのが特徴です。
木材の自然な香りによるリラックス効果
天然木を使用したすのこベッドでは、檜や杉などの木材特有の香りを楽しむことができます。この香りにはリラックス効果があるとされ、質の高い睡眠をサポートしてくれるとされています。
すのこベッドを選ぶ際の重要なポイント
すのこベッドを選ぶ際には、以下のポイントに着目することが大切です。ここでは、それぞれ詳しく解説します。
素材と品質の確認
すのこベッドは素材によって特性が大きく異なるため、用途に応じた選択が重要です。素材ごとの特徴は以下の通りです。
- 桐は軽量で湿気に強い
- 檜は耐久性が高く香りが良い
- 杉・パイン材はコストパフォーマンスに優れる
品質の高い製品を選ぶことで、きしみ音や耐久性の問題を回避できます。
耐荷重の確認
使用する人の体重と寝具の重さを考慮した耐荷重の製品を選ぶことで、安全性と耐久性を確保できます。複数人で使用する場合は、特に注意が必要です。
組み立てやすさとメンテナンス性
部品数が多すぎず、組み立てが簡単な製品を選ぶことで、音の発生リスクを軽減できます。また、定期的なメンテナンスが行いやすい構造かどうかも重要な判断基準です。
すのこベッドが向いている人・向いていない人
すのこベッドを購入するべきかどうか悩んでいる方もいるでしょう。ここでは、すのこベッドが向いている人の特徴・向いていない人の特徴をそれぞれ解説します。
向いている人
すのこベッドが向いている人の特徴は以下の通りです。
- 湿気対策を重視する方
- 軽量で移動しやすいベッドを求める方
- 天然木の香りを楽しみたい方
- こまめな掃除やメンテナンスが苦にならない方
向いていない人
すのこベッドが向いていない人の特徴は以下の通りです。
- 冷えに敏感な方
- 音に神経質な方
- 極端に柔らかい寝心地を好む方
- メンテナンスを面倒に感じる方
自分のライフスタイルや好みを十分に考慮して判断することが大切です。
すのこベッドに関するよくある質問
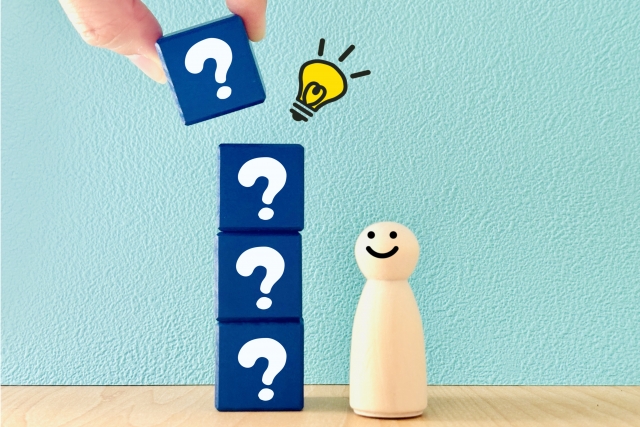
すのこベッドに関するよくある質問について回答します。すのこベッドの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
Q. すのこベッドに布団を直接敷いても大丈夫ですか?
すのこベッドの多くは布団の使用に対応していますが、製品によって異なります。薄い布団の場合、すのこの凹凸を感じることがあるため、ある程度の厚みがある寝具の使用をおすすめします。
Q. すのこベッドのカビ対策はどうすればよいですか?
定期的な換気と、マットレスや布団の天日干しが効果的です。湿度の高い時期は、除湿器の使用も検討しましょう。すのこベッド自体も時々立てかけて乾燥させることが大切です。
Q. 安いすのこベッドと高いすのこベッドの違いは何ですか?
価格差は主に素材の品質、加工の精度、耐荷重に現れます。安価な製品は音が出やすく、耐久性に劣る場合があります。長期的なコストパフォーマンスを考慮して選択することをおすすめします。
Q. すのこベッドのきしみ音を完全になくすことはできますか?
完全になくすことは困難ですが、定期的なメンテナンスと適切な使用方法で大幅に軽減できます。購入時に品質の高い製品を選ぶことが最も効果的な対策です。
Q. 冬の寒さ対策で最も効果的な方法は何ですか?
厚めのマットレスやマットレストッパーの使用が最も効果的です。ベッド下への断熱材の設置や、電気毛布の併用も有効な対策となります。
すのこベッドにはデメリットだけでなくメリットも数多くある
すのこベッドには確かにデメリットがありますが、適切な対策と正しい選び方をすれば、快適に使用できます。「やめたほうがいい」という声がある一方で、その優れた通気性や機能性を評価する声も多く聞かれます。重要なのは、メリットとデメリットを十分に理解した上で、自分のライフスタイルに合った選択をすることです。デメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることで、すのこベッドの良さを最大限に活かすことができます。
名古屋市名東区の大矢家具店では、お客様一人ひとりのライフスタイルやご要望に合わせたベッド選びを丁寧にサポートしています。すのこベッドを含む様々なベッドを実際に見て、触れて、体感していただけます。家具選びのプロがあなたに最適な睡眠環境づくりをお手伝いいたしますので、ぜひ一度、大矢家具店へお越しください。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。